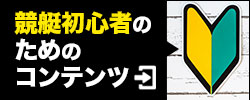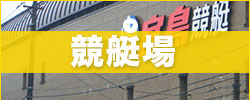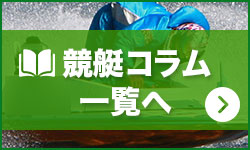競艇の歴史

競艇は日本だけで見ても70年近い歴史があります。
国内では1951年6月18日に公布されたモーターボート競走法制定を受けて1952年4月6日に大村競艇場で公営競技として初開催されました。
公営競技になるまでの歴史
1861年に世界初のモーターボートレースがパリのセーヌ川にてルノアールのガスエンジン搭載ボートで行われました。ガソリンエンジンを搭載したボート競技はドイツのゴットリープ・ダイムラー(15馬力エンジン)が世界初と言われています。
1904年には世界で初めての国際レースがイギリスで行われ、その後アメリカにも広まったと言われています。
国内では1931年7月26日に、隅田川で「第1回船外機艇競走大会」がアマチュア競走として開催されました。1932年には品川台場を発着点にして国内初の長距離耐久競走(56.1km)も開催。
1950年5月に、神奈川県逗子海岸と江戸川で日米対抗の「逗子モーターボートレース」が開催され、これを元に現在の競艇が構築されたと言われています。
翌年1951年6月18日にはモーターボート競走法制定公布されます。同年10月3日に大村選手養成所で選手養成が開始され、11月28日 社団法人全国モーターボート競走会連合会設立認可、と急ピッチで準備が進められていきました。
1952年3月17日に第1回選手資格試験が大津で実施されたこともあり、大津が国内最古のボートレースという意見もあります。
しかし公式競走としては、1952年4月6日開催の長崎県大村競艇場でのレースを最古とするのが一般的です。
海外の競艇事情
元々は、現在のように専用コースを周回するスタイルではなく、海や川を使ったレースでした。
ヨーロッパやアメリカの方が、ボートレース自体が生まれたのは先ですが、公営競技として競艇が現在も行われている国は日本の他に韓国しかありません。
競艇は戦後日本の復興期に、財源の乏しい自治体の貴重な収入源として、競馬を模して実施されたという経緯があります。
隣国の韓国では日本の競艇を真似して1991年に国会で法案が成立。1988年に行われたソウルオリンピックのカヌーとボート競技の会場を改修し、2002年6月にミ沙里漕艇競技場で初開催されました。
日本の競艇の歴史
1952年 大村競艇場で初開催
1953年 若松競艇場で第1回全日本選手権競走を開催
1961年 フライング艇に対する返還欠場が実施
1985年 平和島で初の電話投票を受け付け開始
1988年 グレード制導入、持ちペラ制導入
1997年 桐生でナイター初開催
2000年 3連単導入
2001年 やまと競艇学校開設、ネット投票開始
2002年 スタート展示を実施
2010年 宮島競艇場で減音モーター導入
2012年 新プロペラ制度導入(持ちペラ制廃止)
競艇の歴史は約70年ありますが、3連単や貸ペラ制などが導入されたのは2000年以降であり、ルールや方式を変えながら進化してきました。
ただし、周回数やスタートルールなどの基本は1952年の初開催以降に大きな変更はありません。
オリンピックとモーターボート

長いオリンピックの歴史の中で一度だけモーターボートのレースが競技として採用されたことがあります。
100年以上前の1908年ロンドンオリンピックで、当時流行していた河川を使ったモーターボートレースが開催されました。
公営競技の中では、「ケイリン」が自転車競技のトラックレースとしての種目になっていて、実際にオリンピック出場経験を持つ現役トップ選手も多数います。
エンジンを使った動力でレースを行う競技が採用されたのは、長いオリンピックの歴史で見ても、このモーターボートレースの1回のみです。
1908年ロンドンオリンピックのモーターボート競技
1908年ロンドンオリンピックで初採用されたモーターボート競技は、開催国のイギリスとフランスの2カ国のみが参加しました。
メダルは金メダルのみで3つの競技が開催されました。
結果は以下の通りです。
- 無差別級(フランス)
- 60フィート級(イギリス)
- 8m級(イギリス)
()内は金メダルを獲得した国
名称で分かる通り、一番下のクラスが8m級なので、日本の競艇のような小型ボートではなく、クルーザーのような中型クラス以上のボートを使うレースでした。
60フィート級は18.288m以下の大きさ、無差別級はそれ以上ということで、スピーディな日本の競艇とはかけ離れた内容だったものと思われます。